実は誰にも言っていませんが、(最近片付けていると出てきた)
私、星空博士なんです。
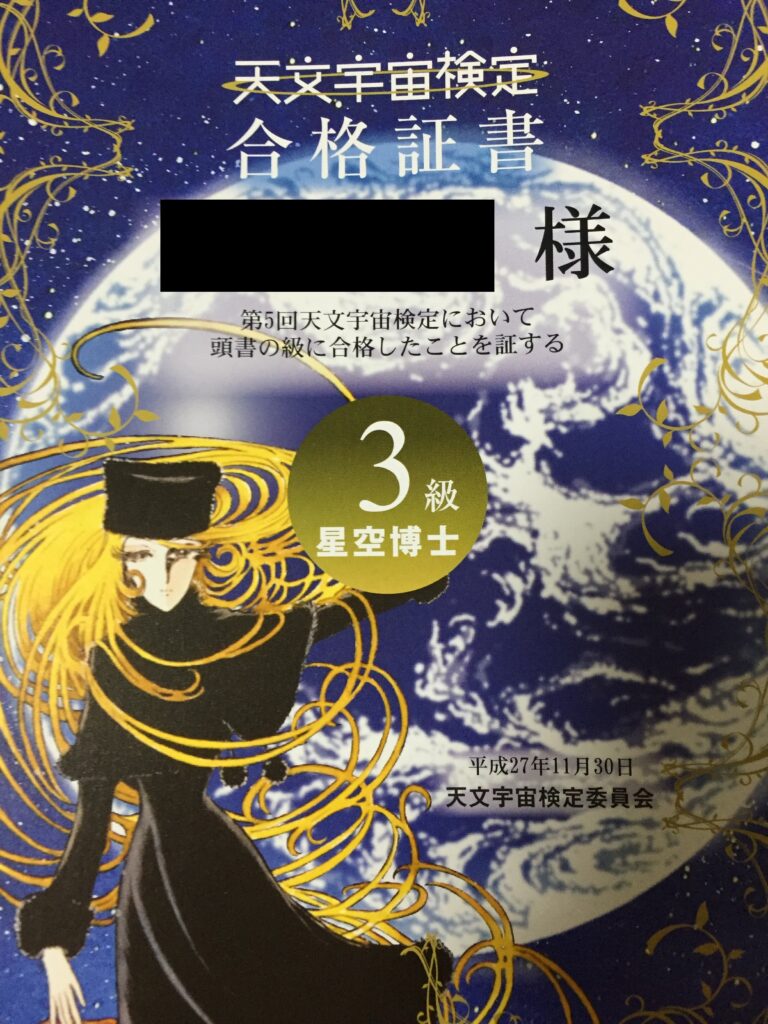
今まで言える場もなく、履歴書にも書けなく誰にも言っていなかったですが、星空宇宙が好きです。
そんな私が書く今回のテーマは太陽!
地球から約1億5000万kmの太陽に行ってみたらどうなるか書いてみました。
光の速さで約8分20秒かかるため、私たちは約8分20秒前の太陽の光を見ている!
🌞 太陽探査機がトライしてる
太陽探査機とは、太陽の構造や活動を観測・研究するために宇宙空間へ打ち上げられた人工衛星や探査機のことです。太陽は私たちの地球に光と熱をもたらす中心的存在であり、その活動は地球の気候や宇宙環境にも大きな影響を与えます。
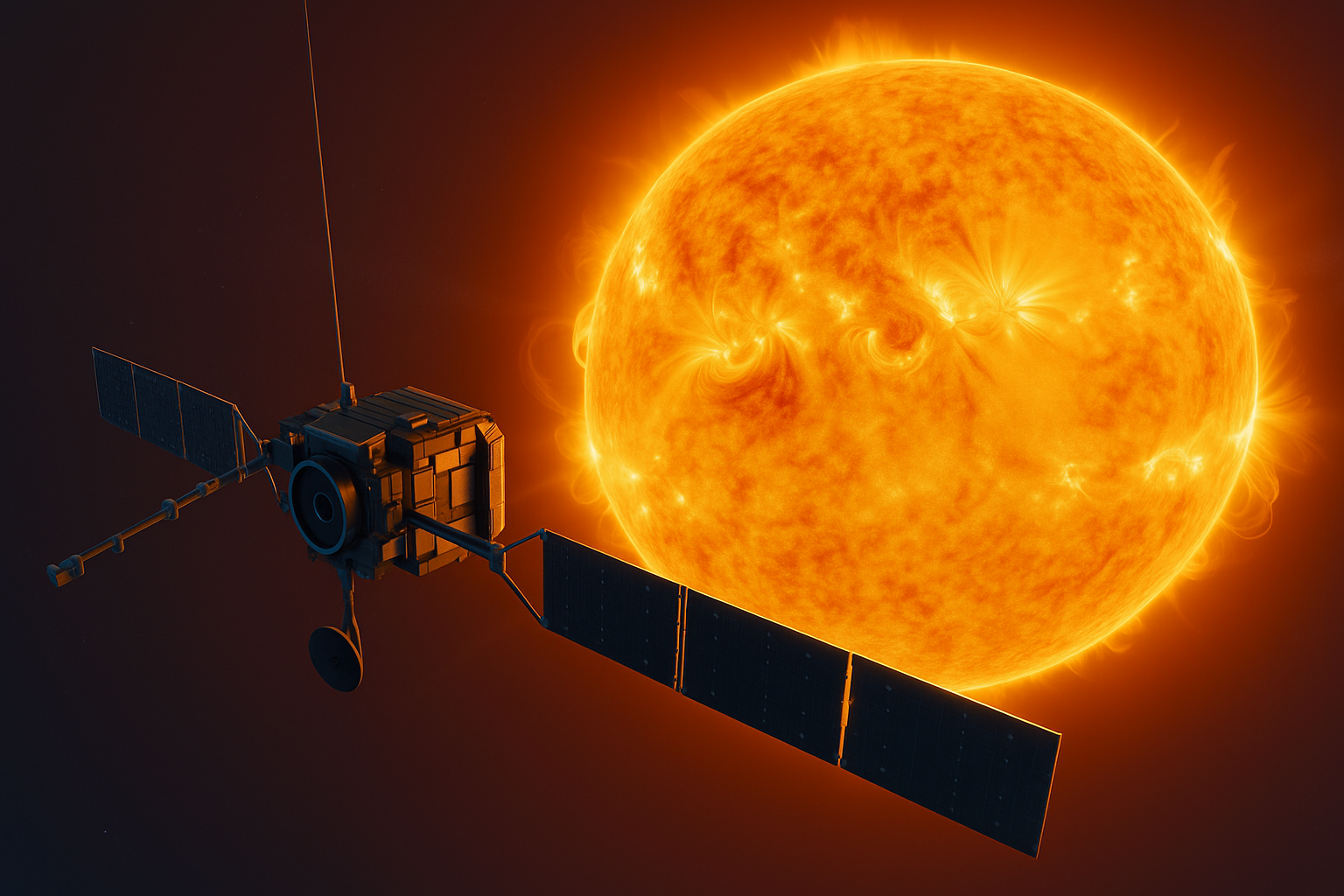
🌍 なぜ太陽を探査するの?
- 宇宙天気の理解:太陽フレアやコロナ質量放出(CME)は、地球の通信や電力網に影響を与えるため、その予測と対策が重要。
- 太陽の仕組みの解明:太陽内部のダイナミクス、磁場の動き、コロナの高温の謎などを調べる。
- 宇宙物理学の進展:太陽は近くにある恒星なので、他の星の理解にもつながる。
🛰 主な太陽探査機
1. パーカー・ソーラー・プローブ(Parker Solar Probe)
- 打ち上げ:2018年(NASA)
- 特徴:史上最も太陽に近づいた探査機(太陽表面から600万km以内に接近)
- 目的:太陽コロナの加熱メカニズムや太陽風の起源を調査
2. ソーラー・オービター(Solar Orbiter)
- 打ち上げ:2020年(ESA・NASAの共同ミッション)
- 特徴:太陽の極域(北極・南極)を観測できる軌道を持つ
- 目的:太陽の磁場と太陽風の関係を研究
3. ひので(Hinode / Solar-B)
- 打ち上げ:2006年(日本/JAXAとNASAなどの国際協力)
- 特徴:太陽の磁場と表面の活動を高解像度で観測
- 成果:黒点や太陽フレアの発生メカニズムの理解に貢献
4. SOHO(Solar and Heliospheric Observatory)
- 打ち上げ:1995年(ESA・NASA)
- 特徴:太陽の内部構造や太陽風を長期間観測
- 成果:太陽の構造やダイナミクス、コロナ加熱、太陽風のメカニズムの解明、多くの彗星も発見(副産物)
リンク
👋 探査機たちの最後はこんな感じ
| 探査機名 | 最終的な運命 | 状態 |
|---|---|---|
| パーカー・ソーラー・プローブ | 太陽に突入して蒸発 | 進行中(2030年代予定) |
| ひので | 通信終了後、地球軌道を漂う | まだ運用中 |
| SOHO | 通信終了後、ラグランジュ点を漂う | 運用中(長寿命) |
| ヘリオス1号・2号 | 宇宙空間を漂流 | ミッション終了 |
| ようこう | 地球大気圏に再突入・燃え尽きた | 終了済み |
☀️ では実際、もしも人類が太陽に行ってしまったら…
1. 🌡 物理的に「太陽に到達」した場合
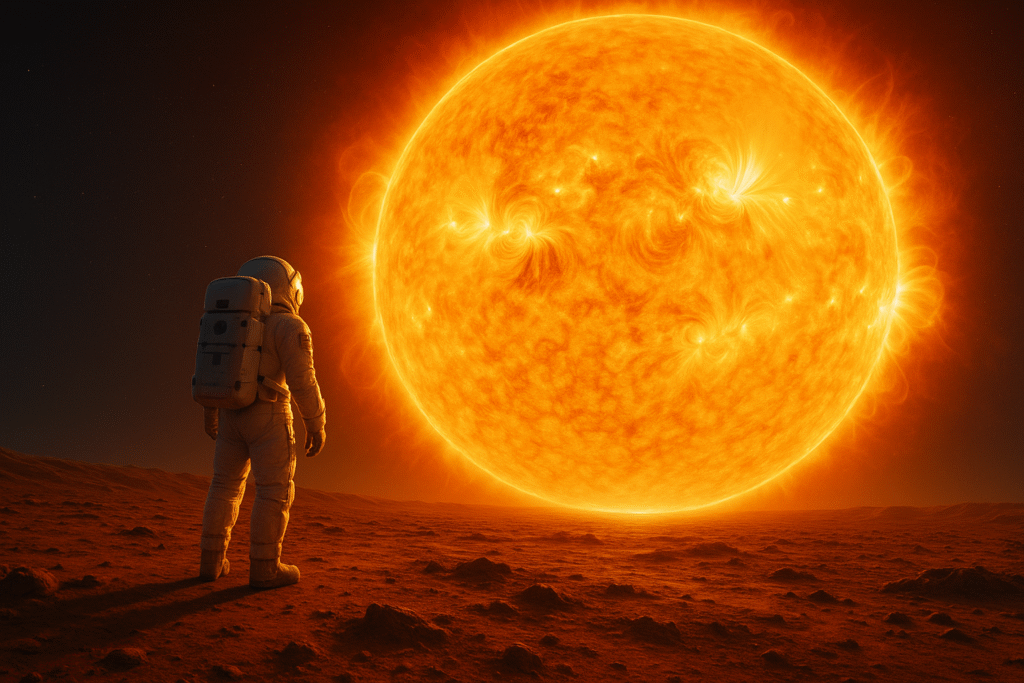
🔥 結末:
- 数百万度の高温(太陽の表面温度:約5,500℃、内部は1,500万℃)により、人間はおろか宇宙船すら即座に蒸発。
- 太陽に近づくだけで、数百万km手前で機器は機能不全。実際、パーカー・ソーラー・プローブでさえ特殊な熱シールドが必要。
🧪 科学的には:
- 人体は約70%が水。数千度の熱で一瞬で気化・分解。
- 金属や炭素系の素材も数分以内に崩壊・蒸発。
2. 🪐 「太陽系内に基地を作って住む」という意味なら…
例えば:水星や金星に住む?
- 水星:昼間は430℃、夜間は−180℃。気温差が激しすぎて居住は困難。
- 金星:気温460℃、大気は二酸化炭素と硫酸の嵐。サウナどころか地獄レベル。
☝️現実には、太陽に「近い」だけで人類の生存はほぼ不可能。
3. 🚀 もし「太陽の中に落ちた」ら
- 太陽の重力に引かれて加速 → 最終的には秒速数百kmで落下。
- 中心部に近づくほど、温度・圧力・放射線が極限状態。
- 落下中にあらゆる分子がバラバラにされ、プラズマ化。
☀️ 結論
現代の人類が太陽に行ってしまったら、生き延びるのは絶対に無理。
でも、太陽を目指すという行為は、科学への好奇心と希望の象徴でもあります。
リンク
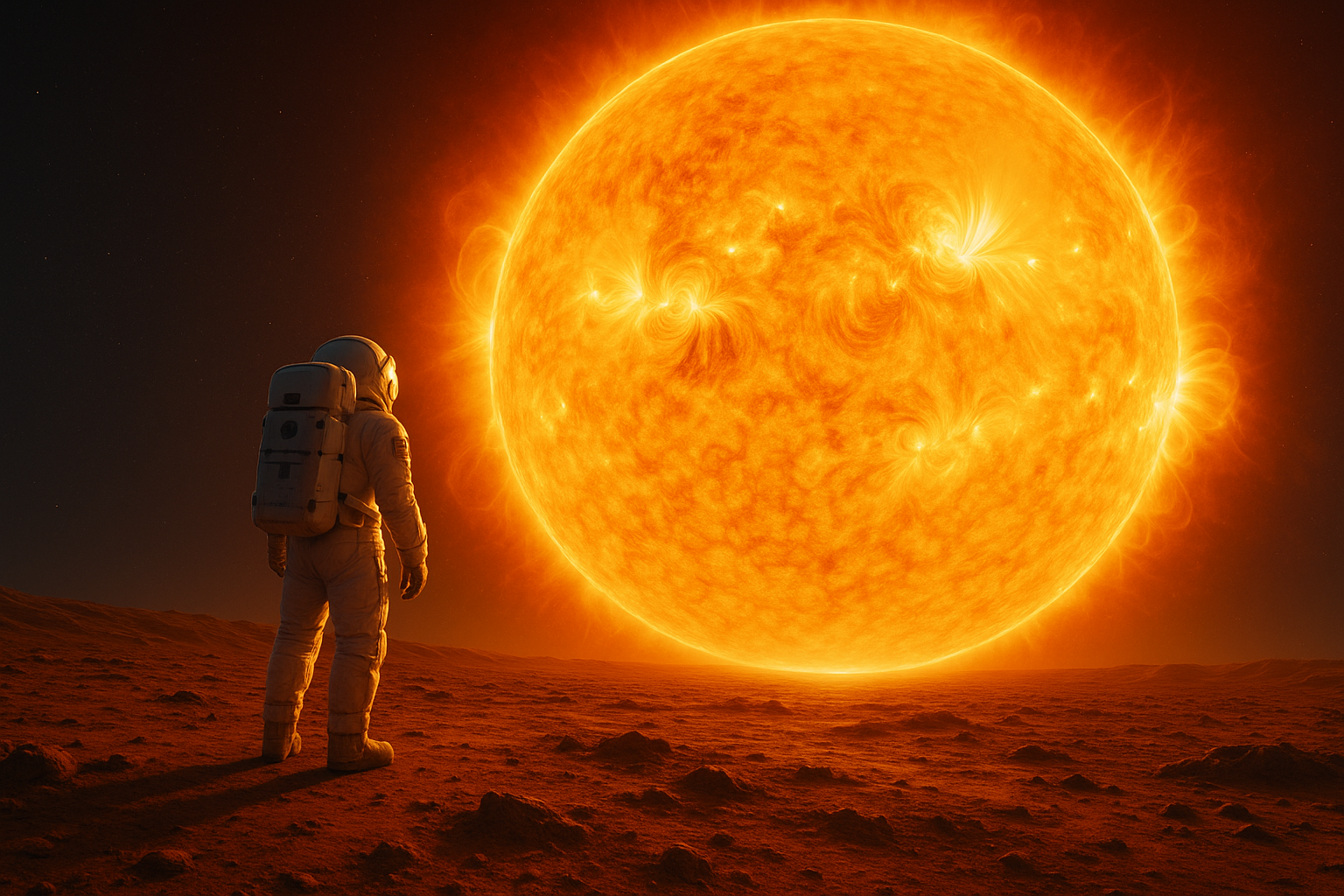


コメント